犬用フェンス完全解説!犬種や大きさに合った選び方などを紹介
犬との暮らしでは、ご自宅の敷地を囲うように、飛び出し・脱走の危険がある場所にフェンスを設置することが重要です

犬がお庭で楽しく安全に遊ぶには、周りを囲うフェンスが必須です。ただ、フェンスは種類や高さ、施工方法などさまざまあり、「愛犬のためにどのようなフェンスを用意したらいいかわからない」という方も多くいらっしゃると思います。
そこでこの記事では、犬のためのフェンス選びのポイントを徹底的に解説。
これまでに紹介してきた「犬のためのフェンス」に関する記事をまとめた内容となっています。わんちゃんのためのフェンス設置に必要なことを全て押さえていますので、ぜひご参考になさってください。
なぜ犬が過ごす家にはフェンスが必要?
まずはフェンスの必要性について解説します。
■犬の安全を守ることが何よりも大切
犬をお庭で遊ばせる場合、足腰に優しい天然芝や人工芝を地面に敷いてあげることも大切ではあるものの、飛び出しを防止するためのフェンスも十分な検討が必要です。
フェンスがないと、遊びに夢中になっている犬はそのまま外に飛び出してしまいます。またフェンスを設置していたとしても、ジャンプ力がある犬種の場合は、フェンスの高さが足りないと飛び越えてしまう場合もあります。
その他、人や車など通行量が多い道に面している庭であれば、外部から犬が危害を加えられないように、目隠しフェンスなどで対策することも重要です。目隠しフェンスは、警戒心の強いわんちゃんの無駄吠えを防ぐことにもつながります。
■お庭遊び中に起きる脱走
犬の脱走は突然起こるものであり、全ての飼い主さんがリスクを把握し、対策しておかなくてはいけません。
犬が脱走する理由の一つは、「習性」によるもの。狩猟のパートナーとして活躍していたルーツをもつ犬種も多く、獲物を見つけたら追い立てるという習性が強いわんちゃんもいます。お庭で遊んでいる際に、視線の先に何か動く物を見つけたら、夢中になって走り出してしまうことがあるのです。その他の習性として、オス犬がメス犬の匂いにつられて、追いかけるために脱走することもあります。
また、「運動不足でストレスが溜まっている」ために、脱走を試みることも。室内にいる時間が長く、散歩ではエネルギーを発散しきれていない場合などは、自由に動き回りたくて脱走してしまうこともあるのです。
■室内にいても脱走は起きる
普段室内で過ごしている犬が脱走するケースも少なくありません。例えば、宅配物の受け取りで玄関を開けた際や、車に乗せようとした際などに、ご自宅の敷地外へ脱走してしまうことがあります。さらに、雷などの大きな音にびっくりして脱走することもあるのです。その他、外に出られるだろうか、フェンスを飛び越えられるだろうか、隙間を抜けられるだろうかといった、単なる好奇心から脱走する犬もいます。
このように、ご自宅の居心地が良かったり、飼い主さんと絆があったりしても、犬は脱走を試みる可能性があります。「うちの愛犬も脱走するかもしれない」といったリスクを把握しておきましょう。
脱走が起こった場合、交通事故に遭う危険や、近隣住民に噛み付くなど危害を与えることも考えられます。犬と人の安全を守るためにも、フェンスや門扉の設置など脱走対策は必須です。
犬が遊べるお庭を作るメリット
お庭のフェンス設置に関連して、そもそも犬をお庭で遊ばせるメリットについても解説します。
愛犬と室内で遊んでいたり、毎日欠かさず散歩に出かけていたりする場合、ご自宅のお庭で一緒になって遊ぶ機会は少ないかもしれません。しかし、外で遊ぶ時間は、犬にとって非常に重要です。「飼い主さんと一緒に外で遊べて楽しい」ということ以外にも、お庭で遊ぶからこそ得られるメリットがあるのです。
まずストレス発散に役立ちます。犬は外に出て、日光・音・匂い・土の感覚などの刺激に触れることを楽しんでいるのです。そのため、室内がいくら快適な環境であっても、好奇心をくすぐる外の空間で自由に過ごしたり遊んだりできないと、犬はストレスを感じることがあります。吠える、噛みつくなどの他、自分の足やしっぽを噛む、体を過剰に舐める・掻くなどの行為は、ストレスサインかもしれません。また、ストレスによって食欲不振や嘔吐・下痢などを引き起こすことも。
もちろん、外で遊ぶ時間が少ないということが、ストレスの主な原因でない場合も多々あります。しかしながら、大好きな飼い主さんと一緒に外で遊ぶ時間があると、わんちゃんは楽しさや安心を感じ、ストレス発散につながるのです。
また、お庭遊びはエネルギーの発散にも効果があります。毎日散歩に出かけている場合でも、犬種や年齢によっては、運動量が足りずにエネルギーが有り余っていることがあります。小型犬であれば15分以上の散歩を1日2回、大型犬であれば30分以上の散歩を1日2回が目安ではありますが、これを守っていてもわんちゃんによっては飼い主さんのペースで歩いていると、十分な運動になっていない場合があるのです。
元気が有り余っているようであれば、散歩に加えて、お庭でボール遊びや引っ張りっこなどをすると、犬はエネルギーを発散することができます。お庭の広さによっては、わんちゃんが自由に走り回れるようなドッグランスペースを設けることもおすすめです。毎日お庭で遊ぶことは難しくても、愛犬の健康のために、休日などにたっぷり時間をとって遊んであげるようにしましょう。
その他、犬をお庭で遊ばせることで、散歩嫌いのわんちゃんのトレーニングになる・脳の活性化になる・飼い主との絆が深まる、などのメリットも得られます。
詳しくはこちらの記事をご参考ください。
≫ 犬を庭で遊ばせるメリットとは?愛犬と楽しむお庭づくりのポイントも紹介
■お庭でノーリードで過ごす場合はフェンス設置が必須
多くの自治体で、フェンスを設けずに犬を放し飼いすることがないよう、条例を定めています。例えば東京都では、「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」の中で、以下のように放し飼いを禁止しているのです。
“犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。” ー東京都動物の愛護及び管理に関する条例
お住まいの自治体の条例をホームページなどで確認し、ルールとマナーを守ってわんちゃんをお庭で遊ばせてあげましょう。
犬のためのフェンスの種類
ご自宅に設置できるフェンスはさまざまな種類があります。犬が過ごすお庭にも適した物もありますので、フェンスの種類ごとの特徴をご紹介します。
■メッシュフェンス
主にスチール素材で作られています。お求めやすい価格で、開放感があり風通しも良いことが特徴です。スチール素材は衝撃に強く耐久性も高いため、ある程度の力はメッシュ形状が衝撃を吸収してくれます。
デメリットとしては、メッシュ状なので目隠しにはならないという点です。また、スチール素材はわんちゃんのマーキング行為で腐る可能性があります。錆止め防止塗料や亜鉛メッキなどを施したフェンスだと安心ですよ。
■目隠しフェンス
外から見えないようプライバシーを守ることができる目隠しフェンス。樹脂製の木目調カラーや、アルミ素材など種類が豊富で、家やお庭のテイストに合わせてデザインを選ぶことができます。
パネルを使った目隠しフェンスなどは、風通しが悪くなったり、圧迫感を感じる場合も。また、木製の場合は耐候性や強度が少し弱いため、腐食のほとんどない金属製の柱を使ったアルミフェンスにすると力の強いわんちゃんが使うドッグランにも合っているでしょう。木目調デザインが施されたアルミフェンスもあるので、デザイン面でも色々と工夫が楽しめます。
一方で、目隠しフェンスの場合は、フェンスとコンクリートブロックの基礎の間に隙間ができるため、カバーを付けるなどしてすり抜け対策をすると良いでしょう。木目調樹脂フェンスで人気のマイティウッドシリーズは、隙間の幅も調整できます。
続いて素材別にフェンスをご紹介します。
■アルミ製フェンス
エクステリアではよく使われる素材で、「丈夫で軽い」「腐食に強い」「加工しやすい」といった特徴があり、アルミの構造材にウレタン樹脂や木粉を吹き付けて様々な色味や木目調カラーを再現することができます。スタンダードな縦格子フェンスから目隠しフェンスまでデザインも豊富です。
■樹脂製フェンス
樹脂を使って木目調などに仕上げることで、木製フェンスよりも耐久性が高くメンテナンスも手軽になり、木の柔らかな風合いも再現できます。またフェンスの板材毎に高さを設計できるので、高さを出したいときにも役立ちます。丈夫なアルミ製の柱と樹脂製の横板を組み合わせて施工することが多いです。
■鋳物フェンス
アルミを溶かして型に流し込んで作る鋳物フェンスは、重厚感や優雅で洋風な雰囲気を生み出すデザイン性の高さが特徴です。耐久性はありますが、隙間が広い物が多く、小型犬がすり抜けてしまう可能性があります。鋳物フェンスは、他のデザインと比べると価格が高いため、自宅ドッグランで採用されるケースは少なく、外周や玄関周りのフェンスとして採用される傾向にあります。
フェンス選びのポイント
犬との暮らしでは、ご自宅の敷地を囲うように、飛び出し・脱走の危険がある場所にフェンスを設置することが重要です。
上記でご紹介したようにフェンスにも色々な種類がありますが、犬が遊ぶ環境向けだけに作られた専用のフェンスは少なく、フェンスを設置する際は犬のための利用を想定していない商品を用いることが多くあります。
そのため、「このフェンスなら安心・安全」と思い込んでしまうことなく、施工の際には犬種・大きさ・性格・自宅環境などに合わせて、愛犬が外に飛び出さないように高さや強度、隙間などを対策しましょう。
■高さ
フェンス選びのポイントとして、まず「高さ」には注意が必要です。例えば、ジャック・ラッセル・テリア、パピヨン、ミニチュア・ピンシャーなどのジャンプ力のある犬種は、大型犬よりも高くジャンプすることもできます。そのため、犬の大きさだけでなく犬種や運動量からフェンスの高さを決めるようにしましょう。
フェンスの高さとしては、およそ1,200mm〜1,500mmが目安とされています。ただし、助走をつけてジャンプできるような場所や、ジャンプ力のある犬種の場合には、1,800mm〜2,000mm以上の高さを確保したいところです。
「愛犬は体が小さいからフェンスを飛び越える心配はない」と判断することなく、犬が本当に飛び越えられないか、よじ登って飛び越えるようなことがないかを施工前に確認しましょう。また施工後は、フェンスの近くに足場になるような物を置かないことも重要です。
■強度
力の強い犬種が勢いよくフェンスに体当たりすることも想定し、「強度」についても考慮が必要です。高さが十分であっても、フェンス自体の強度が低くて倒れたり傾いたりすると、飛び出しを防止することができません。強度が高いフェンスを使い、支柱を十分に補強するなどして、フェンスに強度をもたせることが大切です。またこちらの写真のようにフェンスの基礎部分をブロックにすることで強度を高めるのも有効な方法の1つです。
■隙間
「すり抜け防止」ができているかも確認しましょう。フェンスの目が粗かったり、フェンス下部と地面の隙間が広かったりすると、犬がすり抜けてしまうかもしれません。
フェンス自体の隙間、そして地面とフェンスの隙間は、それぞれ70mm以下にして対策しましょう。小型犬の場合は、50mm以下が理想的です。
ただし、犬によっては穴を掘って隙間を作ってしまうこともあります。こうした場合には、フェンスの基礎にブロックを使うほか、安全な場所に穴掘りが楽しめるスペースを作ってあげると、他の場所では穴掘りをしないようになるでしょう。
犬種別:フェンスの高さ目安
犬の大きさだけでなく、犬種や運動量によってもフェンスに必要な高さは変わります。以下はあくまでも目安のため、わんちゃんが本当に飛び越えられないかを施工前にご確認ください。
■一般的なフェンスの高さ目安
・600mm~ 小型・愛玩犬(チワワ)、小型・牧羊犬(コーギー)
・1,200mm~ 小型・狩猟犬(ジャック・ラッセル・テリア)、中型・作業犬(柴犬)
・1,500mm~ 中型・狩猟犬(イングリッシュ・コッカー・スパニエル)、大型・作業犬(ゴールデンレトリバー)
・1,800mm~ 中大型・牧羊犬(ボーダーコリー)、大型・狩猟犬(シェパード、アフガンハウンド)
※小型犬/体高40cm以下・体重10kg以下、中型犬/体高50cm以下・体重20kg以下、大型犬/体高50cm以上・体重20kg以上ぐらいを想定
■ジャンプ力がある小型犬の場合
トイ・プードル、ミニチュア・ピンシャー、ジャック・ラッセル・テリア、ワイアー・フォックス・テリア、パピヨンなどは小型犬のなかでもジャンプ力があるため、フェンスの高さは「1,200mm〜1,400mm」ほどが目安となります。
名前が挙がっていない小型犬においても、「うちの犬はジャンプ力があるほうだ」と感じられる場合には、脱走防止対策のために1,200mm以上のフェンス設置がおすすめです。
■ジャンプ力がある大型犬の場合
大型犬であれば、目安として1,500mmほどの高さが必要です。
大型犬のなかでも、ジャーマン・シェパード・ドッグ、アフガン・ハウンド、グレーハウンド、ボルゾイなどはジャンプ力があるため、フェンスの高さは「1,800mm〜2,000mm」ほどが目安となります。
目的別:フェンスの施工方法
フェンスの高さや強度を出すために有効な施工方法をご紹介します。
■フェンスの高さを出す方法
市販のアルミフェンスはある程度の高さが決まっています。そのため、ジャンプ力がある犬の場合、フェンスだけでは高さが足りないことがあるのです。その場合には、コンクリートブロックで基礎を作り、その上にフェンスを取り付けるのがおすすめです。
この他、高さや隙間の調節が可能な樹脂フェンス等を用いるのもおすすめです。
■強度を高める方法
体の大きな犬や活発な犬の場合は、勢いよく体当たりして、フェンスが倒れたり隙間が生じたりするかもしれません。フェンスの基礎としてブロック塀を造作し、その上に目隠しフェンスを設置すると、フェンス単体よりも強度が高まるため、建物から離れた所や道路境界など風の強い場所でも安心です。
この他、強度が高いフェンスを使って支柱を十分に補強するという方法もあります。
■すり抜けを防止する方法
フェンスの目が粗かったり、フェンス下部と地面の隙間が広かったりすると、犬がすり抜けてしまうかもしれません。フェンス自体の隙間、そして地面とフェンスの隙間は、それぞれ70mm以下にして対策しましょう(小型犬は50mm以下だと安心です)。写真の樹脂フェンスの場合は、隙間の高さを選べる商品も多いので、わんちゃんの犬種や正確に合わせて選ぶことができます。
■よじ登りを防止する方法
トイ・プードルなど運動能力が高い犬種は、フェンスをよじ登ることもあります。犬は猫と違って、高い所に登った後に自力でうまく降りることができません。飛び降りて着地する際に、関節を痛めたり骨折したりする可能性もあるのです。
そのため、足をかけてよじ登ることが難しい「縦格子」のフェンスを選ぶなど、フェンスの形状も考慮すると、より安全性が高まります。画像のフェンスは、フェンスだけで1,200mmの高さがあるものの、建物のサッシと同じ明るい金属色を使っているので、すっきりと見えます。
また、目隠しフェンスも、足をかけられる隙間が小さいためおすすめです。外からの視線を遮ることもでき、人見知りなわんちゃんのストレス軽減効果もあります。
■ジャンプを抑制する方法
フェンスを飛び越えるようなジャンプは、しつけで止めさせるというよりも、脱走のリスクを減らす環境を作ることが大切です。愛犬が「飛び越えられない」とわかるフェンスを設置することや、お庭からは外が見えない目隠しフェンスを設置することで、ジャンプを抑制することができるでしょう。
フェンスを飛び越えるほどの大きなジャンプ以外に、嬉しかったり興奮したりして、夢中になってその場でぴょんぴょんとジャンプを繰り返すわんちゃんもいます。脱走につながるジャンプではないものの、垂直ジャンプは着地の際に足腰に負担がかかるため、興奮などによる飛び跳ねは止めさせたいところです。
■犬用フェンス設置事例
犬が過ごすお庭のフェンス設置事例をご紹介します。
■木目調の樹脂製目隠しフェンス
お隣との境界には、木目調の樹脂製目隠しフェンスを設置。わんちゃんがお隣の気配を気にして無駄吠えをしないよう配慮しました。フェンスは十分な高さがあり、すり抜けられるような隙間をなくしているため、脱走防止対策もバッチリです。
■芝生にも馴染むナチュラルカラーの目隠しフェンス
こちらのお庭は、天然芝に合わせてナチュラルカラーの目隠しフェンスを設置し、周囲からの視線をカット。愛犬との暮らしやすさを実現しつつ、お家の色味に合わせた外構工事によって、全体が自然味溢れるデザインに仕上がりました。
■ブロックの上にアルミ製の目隠しフェンス
隣地との境界に沿ってブロックを積み、アルミ製の目隠しフェンスを施工しました。高いブロック塀は控え壁を設けたり、基礎をしっかりした物にするなど工事費用がかさみますので、こういったアルミフェンスと組み合わせて高さを出す施工が現在のスタンダードです。また多段フェンスという、より高さのあるフェンスを用いる方法もあります。視線の高さに加えて、愛犬のジャンプ力にも配慮した高さを検討してくださいね。
■フェンスをおしっこから守る方法
犬がお庭でおしっこをする場合、臭いの問題以外に、フェンスなどエクステリアの腐食・サビにつながる懸念があります。
■お庭にトイレスペースを設置して対策
長年にわたっておしっこがかけられると、おしっこに含まれる塩分や尿素が、お庭の木やスチール製のフェンスに悪影響を与えます。また、少々のおしっこならば問題ありませんが、大量にかけつづけてしまうと、尿に含まれる窒素などが天然芝や植物に肥料やけの状態を起こし、変色や枯死につながります。
臭い対策やエクステリアなどを守るための方法として、お庭でおしっこをするわんちゃんには、屋外にトイレスペースを作ってあげてはいかがでしょうか。
方法としてはまず、愛犬のケージ程度のスペースを確保し、ガーデンパンのように区切られた一画を作ります。イメージとしては床をコンクリート、枠をレンガや縁石で施工し、排水工事も行います。そして、レンガや縁石の中に砂や砂利を敷き詰めて完成です。
特に屋外に犬用トイレを設置する際には、多くの愛犬家が「お庭の一角にトイレスペースを設けて、消臭砂利を敷く」という方法を選んでいます。
詳しくはこちらの記事をご参考ください。
≫お庭での犬のおしっこ対策!トイレスペースを作って臭い問題を解消しよう
ウッドデッキにおけるフェンス設置
高さ・強度・隙間・形状がポイント
基本的な考え方は、お庭に設置するフェンスと一緒です。
■高さ
フェンス設置の際には、まず「高さ」を考慮しましょう。例えば、ジャック・ラッセル・テリア、パピヨン、ミニチュア・ピンシャーなどのジャンプ力のある犬種は、大型犬よりも高くジャンプすることもできます。
また、トイ・プードルは狩りを行っていたルーツをもつため運動能力が高く、「1,000mmほどのフェンスを助走なしで飛び越えた」「フェンスをよじ登って乗り越えようとしていた」といった話もあります。
そのため、犬の大きさだけでなく、犬種や運動量からフェンスの高さを決めるようにしましょう。ウッドデッキの場合は助走をつける広さがそれほどありませんので、到達できる高さにも制限がありますが、気になる方はデッキを囲む独立フェンスや前面パネル付きのテラス屋根を併設すると、リスクを抑えられます。
■強度
大型犬などの力の強い犬が勢いよくフェンスに体当たりすることも想定し、「強度」についても考慮が必要です。高さが十分であっても、フェンス自体の強度が低くて倒れたり傾いたりすると、ウッドデッキから外に出てしまいます。人工木のウッドデッキは加工がしやすく、オプションのデッキフェンス以外にも取り付けられるフェンスがありますので、プランナーにご相談ください。
■隙間
フェンスの目が粗かったり、フェンス下部とウッドデッキ床面の隙間が広かったりすると、犬がすり抜けてしまうかもしれません。フェンス自体の隙間、そしてフェンスと床面の隙間は、それぞれ70mm以下にして対策しましょう。小型犬は50mm以下だとより安心です。
■形状
トイ・プードルなど、運動能力が高い犬種は、フェンスをよじ登ることもあります。犬は猫と違って、高い所に登った後に自力でうまく降りることができません。飛び降りて着地する際に、関節を痛めたり骨折したりする可能性もあります。
そのため、足をかけてよじ登ることが困難な「縦格子」や「目隠しパネル」のフェンスを選ぶなど、フェンスの形状も考慮するとより安全性が高まります。
■ウッドデッキのフェンス設置事例
こちらはメーカー主催の施工写真コンテスト「エクステリアリフォーム部門 優秀賞」を受賞した施工事例です。
建物が高い位置にあるお住まいで、手前はオープンなお庭と駐車スペースとなっていますが、ウッドデッキを含めた建物まわりをわんちゃんがドッグランのように自由に歩き回れるよう設計。デッキフェンスはピッチの狭い桟のデザインで、圧迫感を少なくしつつ、わんちゃんがよじ登ることもできない設計です。
フェンスの高さも十分にあり、安全性の高い環境で、わんちゃんもお庭を眺めながらのびのびと過ごせそうですね。
フェンス以外の脱走防止対策
犬の飛び出し・脱走を防ぐために、以下のようなエクステリアやグッズも役立ちます。
■門扉
お庭を囲うフェンスに加えて、門扉の設置も脱走防止に役立ちます。門扉とは、ご自宅の玄関ドアから道路までの間や、勝手口から道路までの間の通行口などに設置する屋外用の扉全般を指すエクステリアです。
犬は予期せぬ行動をとることがあり、例えば宅配物の受け取りなどで玄関を開けた際に、室内にいたはずの愛犬が意図せず外に出てしまうかもしれません。リードを装着している際にも、散歩に出かけられる嬉しさから玄関を飛び出したり、お庭で遊ぶことに夢中になって道路に飛び出したりすることも考えられるでしょう。
急に犬に引っ張られると、リードを持っていても飛び出しを防げない可能性もあり、お子さんの場合は驚いて持っているリードを離してしまうことも考えられます。
こうした場合も、門扉が玄関と道路の間のワンクッションになるため、玄関から愛犬がそのまま道路に飛び出すといった危険を減らすことができます。
設置場所としては「犬走り」「主庭」「門まわり」「駐車スペース」などが主です。主庭だけをドッグランにしたい場合は「お庭の入り口」と「犬走り」に設置するなど、わんちゃんを遊ばせたい範囲に合わせてプランを考えましょう。
詳しくはこちらの記事をご参考ください。
≫愛犬家のための門扉の選び方!飛び出し・脱走防止に役立つエクステリア
■ドッグポール・リードフック
フェンスや門扉のないオープン外構のお庭でも、愛犬を遊ばせたいと思う飼い主さんも多いのではないでしょうか?しかし、囲いのないお庭では、基本的にわんちゃんにリードをつけていないといけませんよね。ただ「ずっとリードを持っていると愛犬が動きにくそう」「ノーリードにできればいいけれど、フェンス設置は難しい」など困っている方も少なくないと思います。
そこでご紹介したいのが「ドッグポール」や「リードフック」です。ドッグカフェや動物病院などで見かけたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?最近ではエクステリアメーカー各社も製造していて、ご自宅のお庭にももちろん取り付けられます。
ドッグポールは、犬のリードを繋いでおくことができる柱状のアイテムです。リードをかけておけるフックが取り付けられていて、リードの長さを調整すれば、犬の行動範囲を広げたり狭めたりすることも自由自在に。ドッグアンカーという言い方をすることもあります。
また、お庭ではなく玄関先や軒下に愛犬を繋ぐ際には、壁に取り付けるリードフックもおすすめです。門柱にも追加で施工できます。
詳しくはこちらの記事をご参考ください。
≫小型・中型犬のいるお庭や玄関に!ドッグポール・リードフックの活用方法と選び方
犬と遊ぶお庭で大切なのは、安全性です。犬がお庭から出てしまわないように、周りをフェンスで囲いましょう。道路と面している部分は特に対策が必要で、フェンスは犬が飛び越えられない高さであることが必須です。すり抜けにも注意しましょう。
犬も飼い主さんも安心して過ごせるお庭環境を整えて、わんちゃんとの楽しい時間をどんどん増やしていってくださいね。

些細なことでも大歓迎!お気軽にお問い合わせください
お庭に関する事なら、ガーデンプラスへお任せください。ガーデンプラスは、全国で外構工事を手掛けるガーデンメーカーです。店舗でのご相談はもちろん、フォームやお電話からのお問い合わせも承っております。
記事に関してのご質問は、外構のプロスタッフがお答えいたします。

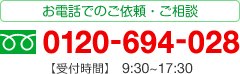



















































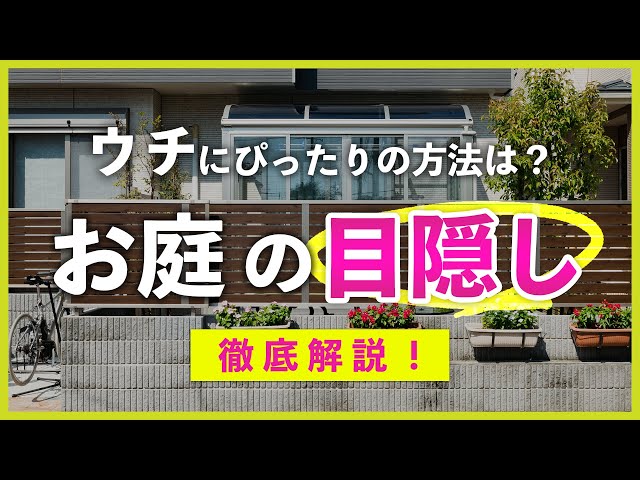

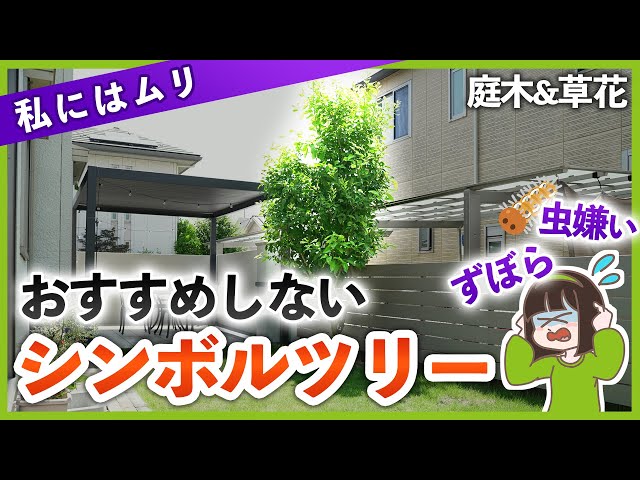



























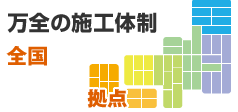

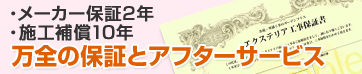

最後までお読みいただき、ありがとうございました。ガーデニングも楽しみつつ、愛犬とも遊べるお庭づくりをお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談ください。
この記事の監修者:DogHuugy
お泊り予約サイト「DogHuggy」や犬とのライフスタイルマガジン
「DogHuggy Magazine」の運営を担当する犬のプロが記事監修を行っています。
プロの目線で愛犬と暮らすお庭づくり・ライフスタイルをご提案します。