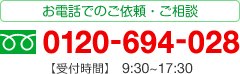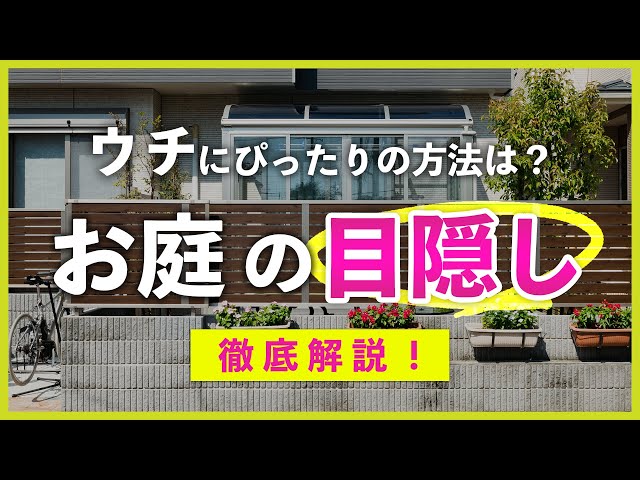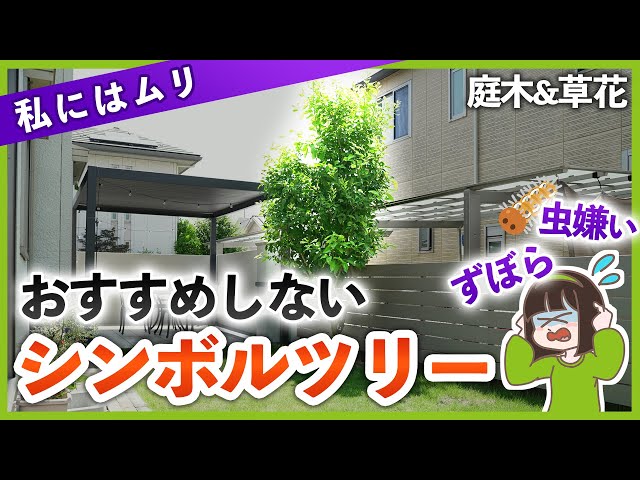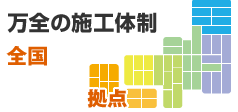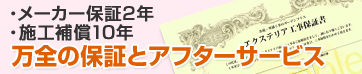剪定入門!清々しい梅の木をお庭に
メンテナンスが難しそうな梅ですが、実は丈夫な性質。剪定にチャレンジしてください!

こんにちは、ガーデンプラスの中川です。
本日は、古くから日本で愛されてきた果樹…梅をご紹介いたします。
突然ですが私の住んでいる借家のお庭には、立派な梅の木があります。入居時にはバッサリと剪定されて葉も何もない状態だったので、何の木かさえ分からなかったのですが、そんな状態でも初夏になるころには新枝がぐんぐんと伸び、1月を過ぎると小さな花が咲きだしました。「梅ってこんなに成長力が強いのか!」と感動したものです。
入居した翌年の写真が残っていました。
やや細くて青い枝が新枝で、半年ぐらいでこれだけ伸びます。この年は何もしていなかったので、いろんな方向に枝が伸びて荒れ放題ですね。そのころは園芸用のハサミさえ握ったことのない私でしたが、さすがに剪定をしないといけないのではと思い、梅について調べ始めました。
現在の私が抱く梅の印象は…梅は病害虫以上に強い、です。さすが奈良時代から日本で野生化しているだけのことはあります。
少し前の日本のお庭ではよく見られた梅ですが、やはりメンテナンスが欠かせないことから、最近の新築のお住まいではなかなか見られることが少なくなりました。それでも冬の庭にまず咲きだす清々しい花と香りは、手間をかける価値を感じます。私もまだまだ勉強中ではありますが、今回は日本の庭の定番・梅の魅力をご紹介いたします。
実ウメと花ウメ
梅と聞いて一番に思い出すのが「梅干し」や「梅酒」などの食べ物ではないでしょうか。中国原産の梅は、本来実を薬として利用するために海を渡ってきました。酸味をもつ調味料としても塩と並んでよく使われていたようです。そういった実を利用するための品種は「実ウメ」と呼ばれ、南高梅で知られる和歌山をはじめたくさんの品種が農家さんのもとで栽培されています。
一方、花を観賞するために交配された梅のグループが「花ウメ」。見た目や香りが良いものが選ばれ、実はほとんどつきません。元々梅自身が自家受粉しにくいのですが、花ウメは特に受粉を手助けしてくれる虫が活動しない寒い時期に花が咲く品種が多いので、実がつかないのも納得です。
見分け方は、実ウメが3~4月に咲くのに対して花ウメは1月~2月から(極早咲きとなると12月から)開花します。また実ウメは白もしくはピンクの一重の花ですが、花ウメには突然変異種である濃い赤の花が存在します。
濃い赤の花は白い花の土台に接木で増やすため、時折先祖返りして白い花が咲くことがあり、一枝に白と赤の両方の花が咲くことも。「思いのまま」「源平咲き」「輪違い」といった名前で呼ばれます。
もしお庭で育ててみたいのでしたら、やはり園芸用の改良種である花ウメをおすすめします。梅の収穫を楽しみたい場合は受粉作業や病害虫の防除が欠かせないですが、花を楽しむだけならば病害虫のいない冬が観賞期なので、剪定のみに気を配ればいいのです。
梅のお手入れ
こちらは夏の梅の木の様子です。若葉をつけながら、空に向かって伸びている枝が分かりますでしょうか?これはすべてその年に伸びてきた新枝で、「徒長枝」と呼ばれます。とにかく光合成するために梅が伸ばした枝なので、枝としてはバランスが悪いのです。写真のような手入れの行き届いた梅園では外側に向かう枝の芽のみ残されていますが、放置している梅の木では内向きや他の枝と交差する枝もたくさん出てきます。
「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」という言葉があるように、庭植えの梅のお手入れは「剪定」に尽きます。シンボルツリーとして人気のシマトネリコも枝をよく出すことで知られていますが、梅も負けていません。しかもシマトネリコと違って、「自然に美しい樹形」になるようには生えないので、剪定が欠かせないのです。
剪定の時期も大切です。7月~8月の一番葉が込み合う時期に不要な枝を切りたくなるものですが、梅では花芽が形成されるため、この時期に切るとエネルギーが新枝に使われるようになり、来年の花が楽しめなくなります。また梅の木は花の後に新枝や新葉を出して成長期に入るため、庭木の剪定のセオリーである開花後に切るのもおすすめできません。剪定時期は落葉して木の形が分かりやすい10月~1月頃。10月になると次の花のための芽が固まり、新枝を伸ばす反応は出なくなります。また木の形自体を整えるために太い枝を切るなら、休眠期の11月頃からです。
剪定の仕方は職人さんによって色々あるのですが、私はこんな感じでやっています。
・春から夏(3月~9月)
風通しをよくするために、こまめに徒長枝の上1/4ぐらいを切る。あまり切りすぎると新枝が伸びてくるので控えめに。
・秋から冬(10月~12月)
落葉すると、夏に切り残した枝や無駄に伸びた枝が分かりやすいので、本格的に樹形を整えるために徒長枝を切る。11月以降は休眠期に入るので、太い枝も剪定OKとなる。
・開花期(1月~2月)
花を楽しむ。
剪定を頑張れば病害虫も減る
ところで皆さんが嫌いな病害虫ですが、バラ科である梅の木ももちろん様々な病気や害虫が発生します。アブラムシ、うどんこ病、バラの天敵である黒星病などなど。しかし病害虫というのは湿気や風通しの悪いところに発生するということ、梅の木がかなり強い性質を持っていることから、日当たりと剪定さえできていれば、意外と防げるように思います。またメンテナンスがしやすいよう、手の届く範囲に樹高を保つようにしましょう。
私の庭の場合は、気づくと樹液を吸うカイガラムシが幹をびっしり覆っていましたが、今のところ毛虫やうどんこ病でひどくやられたことはありません。カイガラムシも地道にこそげ落とし、今は大分減りました(殻を形成すると薬剤が効かないのです…)。アブラムシによって新葉が縮れたこともあるのですが、落葉すると虫の影も形もなくなってしまいます。
植える場所は日当たりのよいところ、水はけのよいところがよいです。日陰に植えると病害虫リスクも高まります。苗木のうちは大きくするための剪定、3年目ぐらいからは樹形や樹高を保つ剪定へと切り替えてくださいね。
剪定を学ぶために…梅園に行ってみよう
今まで剪定がキモだと申し上げてきましたが、初めて剪定をしてみたときに思ったのは「梅ってどんな形が美しいのだろうか」ということでした。理想のイメージが思い浮かばなければ、残す枝も分かりませんよね。
そこでおすすめなのが、梅園や盆栽展に行ってみることです。梅園や日本庭園では職人さんが手入れをしているので、健康で理想的な梅の木を見ることが出来ます。「探梅(うめさぐる)」という言葉は、冬山に春の象徴である梅を探して分け入るという冬の季語ですが、山中で桃源郷のように花盛りの梅園に行き着くと、そんな言葉が思い浮かびます。また梅は盆栽でもよく楽しまれていますが、盆栽の木もまた理想の樹形に整えられているので、勉強するのに役立つと思います。梅にゆかりの深い天満宮で開催されることが多いですよ。この時期は虫や雑草も少ないので、ぜひ植物園や梅園へお出かけしてみてください。
葉がどれだけ病気になっても、たくさんの枝を切られても、年が明けたらケロリとした顔で花を咲かせている…その強健さが庭木としての梅の魅力ではないかと思っています。剪定もコツを抑えて取り組めば、樹勢の旺盛な木なので、失敗しても大丈夫です。夏は青々とした木陰を作り、冬には清々しい花を咲かせてくれる梅。お庭の一画に植えてほしいと思います。

些細なことでも大歓迎!お気軽にお問い合わせください
お庭に関する事なら、ガーデンプラスへお任せください。ガーデンプラスは、全国で外構工事を手掛けるガーデンメーカーです。店舗でのご相談はもちろん、フォームやお電話からのお問い合わせも承っております。
記事に関してのご質問は、外構のプロスタッフがお答えいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。実を収穫したいのでしたら他科受粉させるために2品種を並べて植えてくださいね。うちの梅の品種は未だに分かりませんが、たぶん「野梅系」だと思います。ヤバイ系って読みます。
ガーデンプラス本部
Web担当
中川知春
お客様の目線に立って、お庭の楽しみ方や情報をお伝えしていきたいと思います。